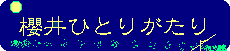「生きてるだけで」
時枝はよく夢を見る。二十歳過ぎで失踪した息子の夢だ。夢の中の我が子は幼い。「おかあたん」と言って、布団の中にもぐりこんでくる。「甘えん坊ね」と笑いながら抱きしめようとすると、すっと虚しく腕の中で消えてしまう。
あの子はもういないんだ!――心臓を握りつぶされるような悲しみに驚き、時枝は目を覚ます。
枕もとの明かりを点け、時計を見る。午前四時前、またこんなに早く起きてしまった。やることなんて何にもないのに。
生来の早起きが、歳を重ねるにつれてひどくなる。せめて若い人のように‘また寝’ができれば少しは一日が短くて済むのに、と彼女はつねづね考えていた。
夢に見た子供の面影は、まだ瞼を去らない。このまま布団の中にいたら、無駄泣きをしてしまいそうだ。仕方なく時枝は床を出た。
布団を押入れにしまい、隅にずらしてあったこたつを部屋の真ん中に据えた。そしていつもの習慣で、テレビのスイッチを入れた。ざあっという音と、細かな点が縞模様をなしてちらつく、いわゆる「砂の嵐」の画面が現れた。月曜のこんな時間に番組をやっている局は無い。せめて音楽が流れるテストパターンの映像でもと、時枝はチャンネル選択のボタンを押しかけた。
だが彼女は思いとどまった。この砂の嵐の音は、胎児が子宮の中で聴く母の血流音に似ている。それが乳児の感情をなごます作用があると、誰かに聞いたことを思い出したからだ。
いっそ赤ん坊になって、どこまでも昔を遡ってやれ――時枝はそんな気持ちで目を閉じた。
ざあっ――それは、彼女の生家の前を流れる川の音だった。雪解けの滴が、流れ星のように光りながら軒を落ち、規則正しい間隔で沓脱ぎ石を打つ。縁側からすべり入る日ざしをよけて布団が敷かれ、彼女はそこに寝かされている。傍らの金盥から、太い湯気が立ちのぼっていた。
優しい祝福の笑顔を浮かべ、自分をのぞきこむ母の顔。
――私が産まれた日か。いや違う、母が若くない。びんに白髪のある初老の顔をしている。だとすれば……そうだ、息子が産まれた日の光景だ。
犬の子のように小さい我が子が、彼女の前に差し出される。
――この子が、こんなに頼りなく小さな子が、今はもう、私を必要としていない。
ふたたび見えない掌が、彼女の心をわしづかみにした。
ぶるっと身震いしてから、時枝はこたつから出た。そして、ゆうべの残りの味噌汁を温めるため流しに立った。テレビは砂の嵐を映し続けている。
マッチで旧式のガスコンロに火をつけた。炎がさっと輪を巻いた。その青さがまたなぜか、時枝の目をひきつけた。けさに限ってどうしたことだろうと訝りながらも、ぽっぽっとすきま風に踊る火を、鍋をかけることも忘れて見つめずにいられなかった。
けっして一心不乱という訳ではない、頭の中で自分に「わたし、こんなんでいいのかな」と、くり返し問いかけた。すると、大きく靡いた炎の蔭から、
「いいんだよ、もういいんだ」という声がした。
たしかに聞き覚えのある言葉だった。遠く記憶をたどるうち、時枝は、末期ガンで病床にあった夫の顔に行き当たった。――いいんだよ、もういいんだ。私は、ただ生きてきただけで幸せだ。かたちあるものを残そうという欲が、人を最期まで苦しめる――。
「いいの? こんなに何もない人生で本当にいいの」
思わずひとり声を発すると、時枝は流しの前にしゃがみこんだ。それからしばらく、背中を震わせて泣いていた。
ざあっ――あの人を送った日も、ちょうどこんな雨降りだった――そんな回想のあと、時枝は‘はっ’とテレビを振り返った。
画面は、相変わらず砂の嵐に被われていた。だが、音も、画像もかたちをなさないブラウン管上に、いま夫のさとすような微笑が浮かびあがった気がしたのだ。
「ただ生きてきただけで…」時枝は泣き笑いしながら立ち上がった。「ほんと、あなたもいいこと言ったわね」
時枝は鍋を火にかけた。すぐに温かい味噌汁の匂いを嗅ぎたくて、いそいでコンロの火力を強めた。
すでに砂の嵐は聞こえない。テレビは、朝の散歩をイメージしたピアノ曲を、六畳の部屋に流しつづけていた。
了
|